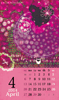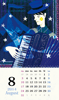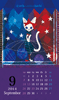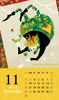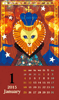「彼の恋、王の愛」
恋する女性が去った後、彼は悲しみのために傲慢な人になり、
やさしかったその瞳は、氷のひかりを放つようになりました。
ショーの時間が終われば暗く沈んだ場所になるサーカス。
彼の冷たい振る舞いに、
傷つく心もありました。
皆が困りはて疲れきったある日、
ライオンが、彼を自分の部屋へ呼び、
自分の椅子へ座らせると、静かな声で語りかけました。
「親愛なる団長よ。
あなたは何処を見ているのです。何をやっているのです。
何故、失った恋にとらわれているのですか。
何故、愛を無くしてしまったのですか。」
「ライオンよ!私が彼女をどれだけ愛しているか
獣のあなたにはわかるまい。
私は彼女に愛される存在だと思っていた。彼女だけが私の望みだったのだ。」
ライオンは少し悲しそうな目でじっと彼をみつめました。
「私が百獣の王であるように、あなたはこのサーカスの王ではありませんか。
王は求めてはいけません。王は与えるべきなのです。」
「何を言うのだ!私が彼女にどれだけ与えたと思うのだ!
私は出来る事をすべてやった。
彼女の美しさを讃え、目に映る美しいものすべてを贈った。
彼女がさらなる名声を得るように、このサーカスも立派にしたのだ。
どれだけ多くの時間と財を彼女のために使っただろう。
なのに彼女は行ってしまった。
これほど愛している私を残して!
今、私に愛が無いというのなら、
彼女を失い、私の中の愛が終わってしまったからだ!」
「サーカスの王よ、それは違う。
愛は終わるものではありません。
与える愛に決して終わりはないのです。
あなたが彼女に贈った愛は、愛ではなかったのでしょう。
それは自分のための恋だった。
ひとりよがりの恋は王にはふさわしくありません。
サーカスの王よ、何故、愛そうとしないのですか。
サーカスの皆を
集まる人々を
輝いているはずのその時間を」
彼の瞳から突然、大粒の涙がこぼれました。
「ああ・・・・ライオンよ・・・・わたしはつらいのだよ。
彼女を失ったことが、こんなにも。
彼女に恋をして私のすべてがかわった。世界は輝いていた。
そして彼女への私の愛は、誰よりも勝っていると信じていたのだ。
今までの想いが自分のためのものだったならば
私には愛するということがわからない・・・。」
「あなたは王です。愛はあなたの中でいつも輝いていました。
今でも必ずそこにあります。
サーカスの皆は待っています。あなたの愛を、あなたの笑顔を。
彼らを幸せにしたいと思わないのですか?」
「ああ・・・もちろんだ。皆が幸せでいてほしい。
そうか、それも愛なのだ。もちろんだ、私は彼らを愛しているのだ。いつまでも愛し続けるだろう。
しかし、彼女へのあの熱い気持ち、
あれこそが私の喜びだったのだ。
・・・あの情熱は、もう求めてはいけないものなのか?」
ライオンは、静かに微笑んで言いました。
「あなたは恋をし続ける人なのかもしれませんね。」
「彼女にか?・・・それでは悲しすぎる」
「いいえ、違います。
親愛なるサーカスの王、あなたは、人生に恋をし続けるでしょう。」
ライオンを見上げた彼の瞳にはおだやかで強い光が戻っているようでした。
団長は少し考えてから言いました。
「そうか・・・そうだね、それもいい。
それこそがサーカスだと思わないか?」
彼は晴れやかな笑顔を見せました。